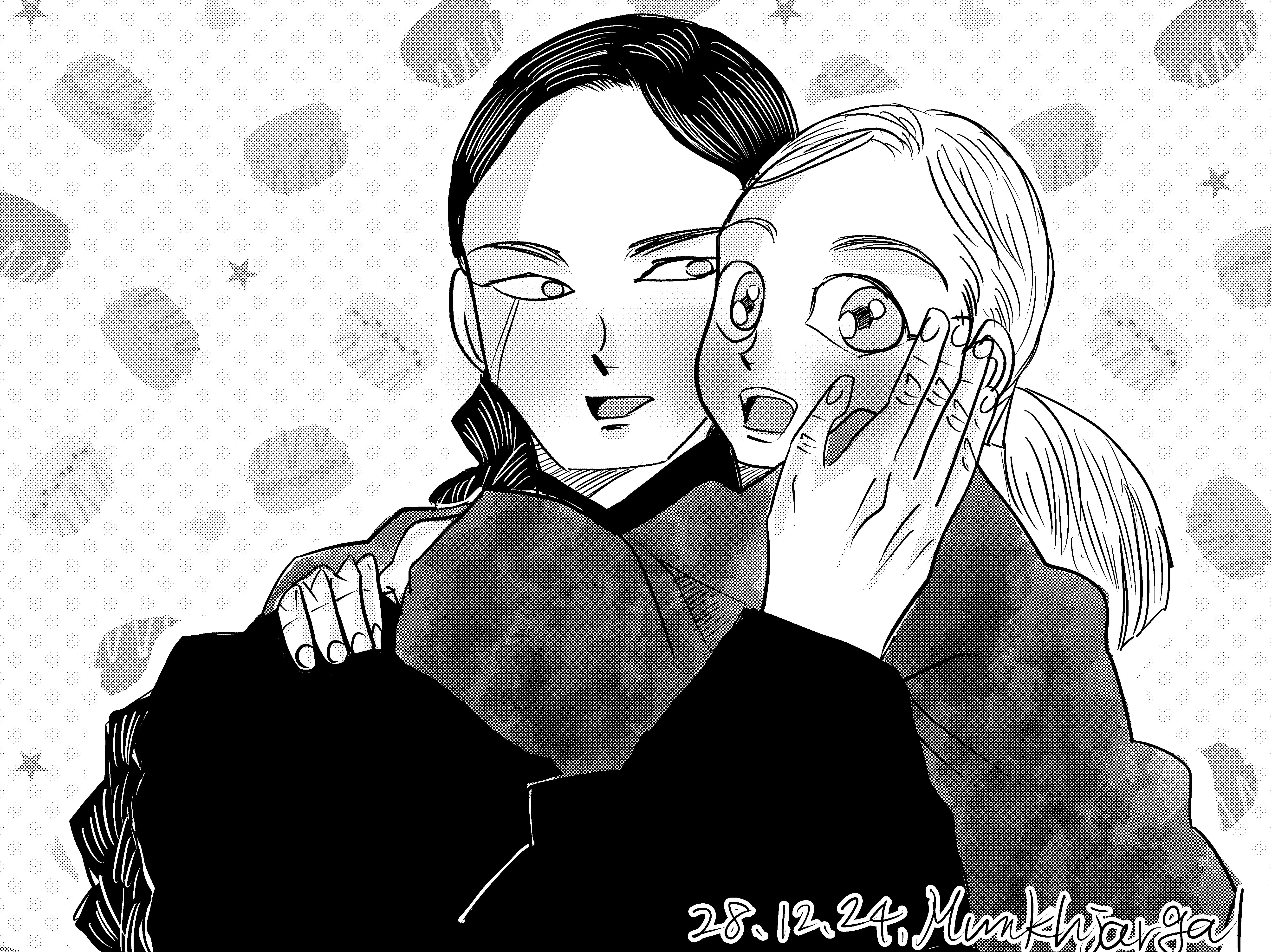SNSはつながってるようで全然つながっていなかった。
生存確認の場?それほど相手の存在が薄っぺらい。
あそこは「印象」の展示場だった
SNSで見えるのって、結局その人の一部分だけなんだよな。きれいに切り取られた瞬間、考え抜かれた一言、反応が欲しくて投げた話題。人格の断片というか、編集された光みたいなもの。
で、私はそこで本気で語ろうとしてた。誠実に心を開こうとしてた。でもそれって、ガラス越しに叫んでるようなものだったんだと思う。声は届いても、触れられない。誰も本当には心を開いてない。開けないようになってる。
SNSって「安全に孤独でいられる場所」なんだろう。
何故か人とつながるほど増していく孤独
あの場所では「共感のふり」と「自己演出」が通貨になってる。本音で語ると浮く。深く考えたことを書くと反応が薄い。軽い話題に軽くノるのが正解みたいな空気がある。
私にはそれができなかった。もともとやれない性分。
結果、誰とも人間関係を築けなかった。でもそれって私の人間性の問題じゃなくて、あの場所の構造の問題だったんだと思う。私の理性が「ここは違う」って直感的に判断してたんだろう。
SNSで仲良くなった人たちの正体
ただ、実際にSNSで仲良くなって、個人的にメッセージのやり取りを深めたりすると、見えてくるものがあった。
問題、闇を抱えた人が多すぎる。
悪口、自慢、愚痴。延々と聞かされる。私は全肯定で応じてた。うんうん、わかる、大変だったね、すごいね、って。でも向こうは私の話にそうじゃない。一方通行。
深い会話はできそうでできなかった。
感情労働で搾取されてる感覚だけが残った。
で、最終的には私がブチ切れて、関係を永久かつ一方的に遮断。毎回こうなる。
リアルだと絶対こうはならない
不思議なのは、リアルで出会った人とは、こういう壊れ方をしないってこと。
リアルの関係って、最初から相互性がある。物理的に同じ空間にいるから、どっちかだけが一方的に喋り続けるとか、どっちかだけが搾取するとかって構造になりにくい。空気が自然に調整される。
でもSNSは違う。テキストのやり取りだけだと、バランスが崩れても気づきにくい。相手の表情も声のトーンもないから、搾取されてることに気づくのが遅れる。そして気づいた時には、もう我慢の限界を超えてる。
SNSで「仲良くなった」と思ってた関係って、実は最初から歪んでたんだと思う。お互いが対等に向き合ってなかった。
リアルな友人に愚痴ってた時点で答えは出てた
皮肉なことに、SNSの愚痴をリアルの人にこぼしてた時点で、私はもう答えを知ってたんだと思う。生の関係性を求めてたんだ。
リアルな関係って面倒くさい。不完全だし、沈黙もあるし、気まずい瞬間もある。でもそこには重力がある。実際に時間を共有してるっていう実感がある。
SNSにはそれがない。全部が軽すぎる。だから虚し過ぎた。
私が求めてるのは共感じゃない
私みたいな人間に必要なのは共感じゃなくて、誠実な共存なんだと思う。
わかり合えなくてもいい。沈黙を許せる距離。会話が続かなくても気まずくならない関係。気配で信頼が成り立つような、そういうつながり。
それってSNSでは絶対に生まれない。でも現実のどこかで、時間をかけて少しずつ育っていくものだと思う。派手じゃないけど。
疲れたのは、見抜いてしまったから
結局、私がSNSで感じた疲労感って、あの場所の限界を見抜いてしまった感受性の副作用だったんだと思う。
表層的なつながりに満足できない。本質的な関係性を求めてしまう。その感覚が疲労を生んでた。
でもこれって欠陥じゃない。何が本物で何が幻かを見分ける能力なんだと思う。その能力を持ってる人は、SNSの限界を早く見抜く。そして離れる。
それは敗北じゃなくて、正確な認識に基づいた選択なんだと、今はそう思ってるよね。
🐈登場人物紹介へ戻る
🐇HPへ